第20回の試験で初めて出題されましたね。
これ系の問題は覚えておけば点数が取れますので試験前に簡単に復習しておくことをおすすめします。
認定試験まであともう少しですから勉強するにはいいタイミングかもしれません。
ただ覚えるだけなので正直あまり面白い記事じゃないですけど試験までもうちょっとなので頑張ってください!
背景
「背景」・・・とか、「概要」・・・とか、もう読む気力が失せますね。
書いている僕も辛いです。
ではまずどんな問題が出題されたか確認しましょう!
20-問題50 「肝 MR エラストグラフィ撮像・管理指針(2022 年 3 月 23 日 日本医学放射線学会理事会承認)」について正しいのはどれか。2 つ選べ。
1. 1.5 T もしくは 3 T の装置で撮像する。→○
2. 臨床で使用するにあたり、事前に 1 名以上のボランティア撮像を行う。→×事前に5名以上のボランティア撮像を行う
3. 専用の加振装置の定期的な点検などを磁気共鳴専門技術者が 5 年に 1 回以上確認を行うこと。→×磁気共鳴専門技術者あるいはそれに準ずる者が1年に1回以上確認を行うことが望ましい
4. 肝 MR エラストグラフィ画質管理者は画質の管理とともに、他の施設との互換性を担保し、標準的な保険医療を目指すことが望まれる。→○
5. 肝 MR エラストグラフィ画質管理者を磁気共鳴専門技術者あるいはそれに準ずる者、放射線診断専門医、および肝臓専門医の中から 1 名定めること。→×「磁気共鳴専門技術者に準ずる者」は無し
こんな感じです。
鎮静の指針や安全運用指針などに比べると内容は少ないので要点だけ覚えましょう。
では背景として、日本磁気共鳴医学会が日本医学放射線学会・日本肝臓学会・日本門脈圧亢進症学会と共同で提案した肝MRエラストグラフィが2022年度診療報酬改定で保険収載(保険適用のリストに登録されること)となりました。
上記の「⑤学会が定める指針に基づくこと」これが今回の記事のお話となります。
指針のお話
指針は主に検査方法、検査と画像評価の精度管理、装置の安全運用管理の3つから構成されます。認定試験でも問われやすいのはこのあたりかと思います。
ではまずMRエラストグラフィについてです。
肝線維化の診断に最も信頼がおけるのは肝生検である。
しかし肝生検で得られた検体は肝組織の一部分のみであること、侵襲的であること、入院が必要で費用が高いこと、肝生検の繰り返しは困難であることなど課題が多い。
肝生検以外の肝線維化を評価する非侵襲的な検査は、「血液生化学的検査」「超音波エラストグラフィ」「MRエラストグラフィ」があり中でも「MRエラストグラフィ」は早期にかつ正確に肝線維化を診断することができるとの報告がある。
検査方法
ここら辺から重要かもしれません。
①1.5T もしくは 3Tの装置で撮像する。
②薬事承認を得た専用の体外加振装置を使用する。
③仰臥位での撮像とする
④パッシブドライバは鎖骨正中線の剣状突起の高さにある右側の胸壁の上に設置する。パッシブドライバは胸壁に密着するように伸縮性バンドで固定する。
⑤スライス位置は肝門部よりやや頭側で、横断面において肝臓ができるだけ広範囲に描出されるような位置とする。
⑥各種シーケンスの推奨撮像条件は日本磁気共鳴医学会のホームページに掲載されている推奨撮像条件を参照するか、北米放射線学会(RSNA)の(QIBA)が定める条件を参照すること。
⑦位相画像、波画像、硬度マップ(弾性率マップ)、信頼度マップを得られる適切なシーケンスで撮像する。
⑧撮像者はGREもしくはSE-EPIの撮像直後に強度画像を確認して、撮像不良がないことを確認する。
⑨撮像を行う者についてはパッシブドライバの設定位置等の撮像法について院内で研修を行い、個人間の差異がなくなるように努めること。
検査と画像評価の精度管理
①臨床で使用するにあたり、事前に5名以上でボランティア撮像を行い、加振装置のパッシブドライバの被験者体表への設置部位・方法や息止め方法、撮像を行うMRI操作者の違いなどによる測定値のばらつきを最小限とし、繰り返し精度を可能な限り向上させ、それを維持するための管理体制を整える。
なお、同一のボランティアを繰り返し撮像する際は一度ボランティアが寝台から降りた状態から再度撮像すること。なお、肝硬度のデータは日本磁気共鳴医学会のホームページよりダウンロードして記入すること。
②肝MRエラストグラフィ画質管理者を日本磁気共鳴専門技術者認定機構が認定する磁気共鳴専門技術者、日本医学放射線学会が認定する放射線診断専門医、および日本肝臓学会が認定する肝臓専門医の中から1名を定め、肝MRエラストグラフィ画質管理者のもと、精度管理体制を整える。
③臨床における肝硬度評価については、放射線診断専門医および肝臓専門医が協力して評価する体制を整えることが望ましい。
④関心領域は位相画像、波画像、硬度マップ(弾性率マップ)、信頼度マップの各種画像を参照してできるだけ大きく、適正な波(coherent wave)の伝搬部位を測定する。また、心拍動の影響が大きな肝左葉外側区域は避け、原則的に右葉で測定する。また、大血管や肝表近傍、病変、信頼度の低い部位を避ける必要があるので、フリーハンドで関心領域を設定することが望ましい。特に波画像をシネ表示で観察し、hot spotやdark spotを避けることが重要である。
⑤肝MRエラストグラフィ画質管理者は画質の管理とともに、標準的な保険医療を目指すために、できるだけ他の施設との互換性を高めるよう努めることが望まれる。日本医学放射線学会による認証を必要とし、撮像条件や各種画像(GRE もしくは SE-EPI などの強度画像、 位相画像、波画像、硬度マップ、信頼度マップ)、年間の肝臓MRI検査件数と肝MRエラストグラフィ加算の件数の情報を提出し、標準的かつ適正な肝MRエラストグラフィの保険医療の運用に協力することが望ましい。なお、提出する撮像条件は日本磁気共鳴医学会のホームページより指定のエクセルファイルをダウンロードして使用し、画像はPower Pointへキー画像(波画像は動画)を貼り付けて提出する。
装置の安全運用管理
①日本磁気共鳴医学会と日本医学放射線学会が定める臨床MRI安全運用のための指針に基づき、MRI 装置の安全管理を行なっている。
②専用の加振装置(アクティブドライバ、パッシブドライバを含む)の定期的な点検に加え、当該装置が正常に動作しているかどうかの確認と破損等がないことを肝MRエラストグラフィ画質管理者の監督のもと磁気共鳴専門技術者あるいはそれに準ずる者が年に1回以上確認を行うことが望ましい。肝MRエラストグラフィ画質管理者はさらにその内容を日本医学放射線学会に報告する。
さいごに確認しましょう
文章だけ読んで覚えた気になっても、実際に試験問題で問われたら案外忘れていることが多いものです。
時間があったら以下の確認問題もやってみてください。
検査方法について
①1.5T もしくは 3Tの装置で撮像する。
○
②薬事承認を得た専用の体外加振装置を使用する。
○
③撮像体位は問わない
×仰臥位での撮像とする
④パッシブドライバは鎖骨正中線の剣状突起の高さにある左側の胸壁の上に設置する。パッシブドライバは胸壁に密着するように伸縮性バンドで固定する。
×右側の胸壁
⑤スライス位置は冠状断において肝臓ができるだけ広範囲に描出されるような位置とする。
×肝門部よりやや頭側で、横断面において肝臓ができるだけ広範囲に描出される位置
⑥各種シーケンスの推奨撮像条件は日本医学放射線学会のホームページに掲載されている推奨撮像条件を参照するか、日本磁気共鳴医学会が定める条件を参照すること。
×日本磁気共鳴医学会のホームページに掲載されている推奨撮像条件 or 北米放射線学会(RSNA)の(QIBA)が定める条件を参照
⑦位相画像、波画像、硬度マップ(弾性率マップ)、信頼度マップを得られる適切なシーケンスで撮像する。
○ 磯野波平は頑固だが信頼できる(語呂)→位相画像、波画像、硬度マップ、信頼度マップ
⑧撮像者はGREもしくはSE-EPIの撮像直後に位相画像を確認して、撮像不良がないことを確認する。
×強度画像
⑨撮像を行う者についてはパッシブドライバの設定位置等の撮像法について院内で研修を行い、個人間の差異がなくなるように努めること。
○
検査と画像評価の精度管理について
①臨床で使用するにあたり、事前に3名以上でボランティア撮像を行い、加振装置のパッシブドライバの被験者体表への設置部位・方法や息止め方法、撮像条件の違いなどによる測定値のばらつきを最小限とし、繰り返し精度を可能な限り向上させ、それを維持するための管理体制を整える。
①臨床で使用するにあたり、事前に5名以上でボランティア撮像を行い、加振装置のパッシブドライバの被験者体表への設置部位・方法や息止め方法、撮像を行うMRI操作者の違いなどによる測定値のばらつきを最小限とし、繰り返し精度を可能な限り向上させ、それを維持するための管理体制を整える。
同一のボランティアを繰り返し撮像する際は一度ボランティアが寝台から降りた状態から再度撮像すること。なお、肝硬度のデータは日本磁気共鳴医学会のホームページよりダウンロードして記入すること。
○
②肝MRエラストグラフィ画質管理者を日本磁気共鳴専門技術者認定機構が認定する磁気共鳴専門技術者あるいはそれに準ずる者、日本医学放射線学会が認定する放射線診断専門医、および日本肝臓学会が認定する肝臓専門医の中から1名を定め、肝MRエラストグラフィ画質管理者のもと、精度管理体制を整える。
×磁気共鳴専門技術者 or 放射線診断専門医 or 肝臓専門医 ※磁気共鳴専門技術者に準ずる者は含まれない
③臨床における肝硬度評価については、磁気共鳴専門技術者、放射線診断専門医および肝臓専門医が協力して評価する体制を整えることが望ましい。
×磁気共鳴専門技術者は含まれない
④関心領域は位相画像、波画像、硬度マップ(弾性率マップ)、信頼度マップの各種画像を参照してできるだけ大きく、適正な波(coherent wave)の伝搬部位を測定する。また、心拍動の影響が大きな肝左葉外側区域は避け、原則的に右葉で測定する。
○
測定では肝表近傍、病変部位で測定する必要があるので、フリーハンドで関心領域を設定することが望ましい。特に波画像をシネ表示で観察し、hot spotやdark spotを測定することが重要である。
×大血管や肝表近傍、病変、信頼度の低い部位を避ける必要があるので、フリーハンドで関心領域を設定することが望ましい。特に波画像をシネ表示で観察し、hot spotやdark spotを避けることが重要である。
⑤肝MRエラストグラフィ画質管理者は画質の管理とともに、標準的な保険医療を目指すために、できるだけ他の施設との互換性を高めるよう努めることが望まれる。
○
日本磁気共鳴医学会による認証を必要とし、撮像条件や各種画像(GRE もしくは SE-EPI などの強度画像、 位相画像、波画像、硬度マップ、信頼度マップ)、年間の全MRI検査件数と肝臓MRI検査件数の情報を提出し、標準的かつ適正な肝MRエラストグラフィの保険医療の運用に協力することが望ましい。なお、提出する撮像条件は日本磁気共鳴医学会のホームページより指定のエクセルファイルをダウンロードして使用し、画像はPower Pointへキー画像(波画像は動画)を貼り付けて提出する。
×日本医学放射線学会による認証を必要とし、撮像条件や各種画像(GRE もしくは SE-EPI などの強度画像、 位相画像、波画像、硬度マップ、信頼度マップ)、年間の肝臓MRI検査件数と肝MRエラストグラフィ加算の件数の情報を提出し、標準的かつ適正な肝MRエラストグラフィの保険医療の運用に協力することが望ましい。なお、提出する撮像条件は日本磁気共鳴医学会のホームページより指定のエクセルファイルをダウンロードして使用し、画像はPower Pointへキー画像(波画像は動画)を貼り付けて提出する。
装置の安全運用管理について
①日本磁気共鳴医学会と日本磁気共鳴専門技術者認定機構が定める臨床MRI安全運用のための指針に基づき、MRI 装置の安全管理を行なっている。
×日本磁気共鳴医学会と日本医学放射線学会が定める臨床MRI安全運用のための指針に基づき、MRI 装置の安全管理を行なっている。
②専用の加振装置(アクティブドライバ、パッシブドライバを含む)の定期的な点検に加え、当該装置が正常に動作しているかどうかの確認と破損等がないことを肝MRエラストグラフィ画質管理者の監督のもと磁気共鳴専門技術者あるいはそれに準ずる者が年に2回以上確認を行うことが望ましい。肝MRエラストグラフィ画質管理者はさらにその内容を日本医学放射線学会に報告する。
×年に1回以上確認
ちょっと問題が長くなりましたがいかがでしたでしょうか。
認定試験に出題されるかはわかりませんのでこちらの記事はさらっと読んでみてくださいね。
では頑張ってください!

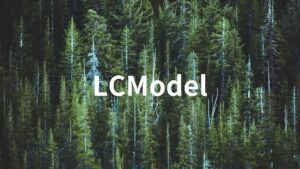
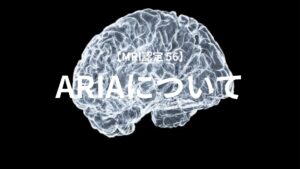

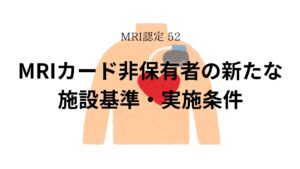

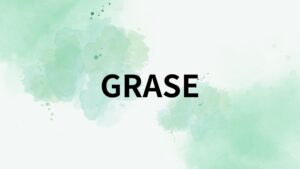



コメント