認定試験で出るかわかりませんが出そうな気もするので簡単にですがまとめておきます。
概要
アルツハイマー病の薬は、神経細胞の間の伝達を調整することによって症状を和らげる働きのものしかありませんでした。
以前はアルツハイマーの根本的な治療を行う薬はなく、キムタクが如く(JUDGE EYES)というゲームでも扱われたりと夢のような薬となっていました。
しかし新しく抗アミロイドβモノクロ-ナル抗体(抗Aβ抗体)という製剤が承認され、こちらはアルツハイマーの原因となるアミロイドβを除去する作用を持っています。
アミロイドβ
アミロイドβとは正常な脳でもつくられるのですが、排出も行われているため過剰に蓄積しないようバランスがとられています。
この排出にGlymphatic systemが関係しているのですが過去の記事にも少し書きましたので良ければ見てみてください。→Glymphatic system
このバランスが崩れ、徐々にアミロイドβが蓄積されプラークなどの固まりとなり、神経細胞が死滅していくことで認知機能が低下していくと考えられています。
では、このアミロイドβをなくせばアルツハイマーは治せるのでは?というのが抗Aβ抗体という薬となります。
抗Aβ抗体の有害事象
抗Aβ抗体は有効性が期待される一方で、アミロイド関連画像異常(Amyloid-related imaging abnormalities:ARIA)という有害事象が発生する可能性があります。
このARIAは、ARIA-EとARIA-Hの2つに分類され、ARIA-Eは脳実質の脳浮腫または滲出液貯留、ARIA-Hは微小出血または脳表ヘモジデリン沈着が認められます。
ARIAが認められた場合は投与継続か中止を判断しなければならず、MRI画像と臨床症状両方の重症度をみて判断することとなります。ARIAを早期に検出および鑑別し、経過を観察することが患者さんの安全性のために重要となります。
ARIA
ARIAの起こる機序
脳実質や血管などに蓄積したAβプラークに抗Aβ抗体が結合し除去されることにより、血管壁の透過性が破綻して蛋白液や赤血球が血管外に漏出する。血漿成分が漏出するとARIA-E、血球成分が漏出するとARIA-Hとなると考えられている。
ARIAの発現は製剤投与から14週以内に多く、特に注意深く患者の様子を観察することが推奨されています。
ARIA-E(浮腫・滲出液)
脳実質における血管原性浮腫のみでなく脳溝における滲出液貯留
FLAIRで評価
脳実質の浮腫だけでなく、髄軟膜の滲出液貯留を評価する必要があるためCSFを抑制できるFLAIRを用いることとなります。
| 重症度 | 画像所見 |
| 軽度 | 脳溝、皮質、皮質下白質の1ヵ所に限局した、5cm未満のFLAIR高信号 |
| 中等度 | 最大径が5~10cmのFLAIR高信号が1ヵ所にみられる、又は10cm未満の高信号が複数部位にみられる。 |
| 重度 | 10cmを超えるFLAIR高信号で、脳回腫脹及び脳溝消失を伴う。1ヵ所又は複数ヵ所に独立した病変を認める。 |
ARIA-H(出血・へモジデリン沈着)
脳実質における微小出血のみでなく脳表ヘモジデリン沈着
GRE(T2*)またはSWIで評価
| 重症度 | MRI所見(微小出血) | MRI所見(へモジデリン沈着) |
| 軽度 | 新規が1~4個 | 1ヵ所 |
| 中等度 | 新規が5~9個 | 2ヵ所 |
| 重度 | 新規が10個以上 | 3ヵ所以上 |
MRI撮影
治療を開始する前に、直近1年以内のMRIを入手すること。5回目、7回目、14回目の投与前にMRIを撮影することとなっております。
ARIAは製剤投与から14週以内に多く、ARIAを示唆する症状がみられた場合は臨床評価を行い、必要に応じてMRIを実施します。
磁場強度は1.5T以上。3.0Tが推奨される。
スライス厚5mm以下
FLAIR
ARIA-Eの浮腫と滲出液の検索
3Dの方が検出感度が高い
T2* SWI
微小出血とヘモジデリン沈着の検出
SWIの方が微小出血の検出感度が高い
DWI ADCmap
急性期脳梗塞との鑑別
ARIA-Eの浮腫と鑑別するため
まとめ
ARIA-E:脳実質における血管原性浮腫と脳溝における滲出液貯留 FLAIR
ARIA-H:脳実質における脳微小出血および脳表ヘモジデリン沈着 T2*/SWI
ARIAは投与14週以内に多い
磁場は1.5T以上、スライス厚は5mm以下
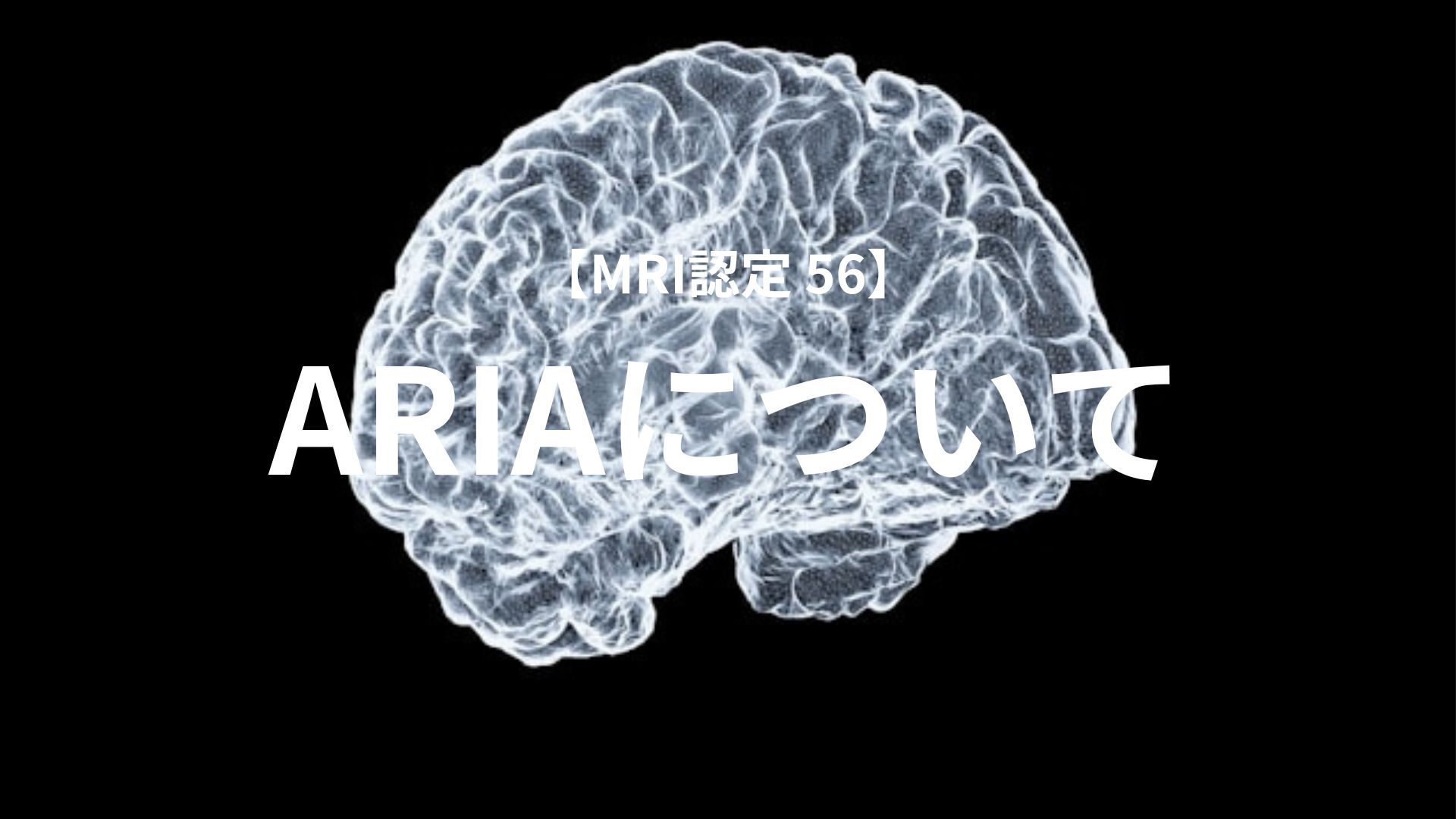





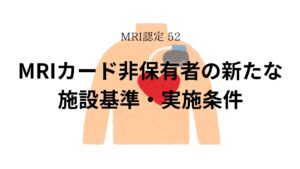


コメント