膵臓の所見に関しての問題です。
問題
16) 膵臓の MRI について、正しい文章を解答して下さい。
a.膵臓の内包する高蛋白により、T1 強調画像において腹部で最も信号の高い臓器である。
b.T1 強調画像に脂肪抑制を付加することにより、膵臓の輪郭を明瞭に描出できる。
c.膵臓の腺癌は、動脈相で周囲の膵実質より強く造影される。
d.膵島細胞腫瘍の多くは、T2 強調画像にて高信号を呈し、動脈相において膵実質より増強効果は弱く、低信号域として描出される。
e.腫瘤形成性膵炎と膵臓癌の鑑別としては、内部の均一性、造影効果などが挙げられる。
解答
a,b,e
解説
正常膵臓の信号と膵癌の信号
膵臓には消化酵素を産生・分泌する膵腺房細胞が存在し、膵臓の9割以上を占めています。膵腺房細胞は高蛋白含有水であるためにT1WIでは高信号となります。(高信号と言っておりますが皮下脂肪みたいな強いものではなくグレーだけど明るいかなくらいに思ってください)
癌には膵腺房細胞が存在しないため低信号となりコントラストがつきます。
しかし膵炎となることで膵腺房細胞が減少し線維化するためにコントラストは悪くなります。
脂肪抑制T1WIでは内臓脂肪が低信号となるために、より膵臓が明確にコントラスト良く描出されます。
T2WIでは実質は低信号、膵管は高信号となります。また嚢胞があった場合液体成分を反映して高信号となります。
ダイナミックについて、正常な膵臓実質は血流が比較的多いために早期に染まり、しだいに造影効果は減っていきます。逆に膵癌では線維性間質のために早期では造影効果が乏しく、遅延相にてだんだん染まっていきます。
DWIでは膵癌は高信号、そしてADCで低信号となります。
膵癌のほとんどは管状腺癌です。これら説明はこの管状腺癌についてしましたが、膵癌には他にも種類があり典型的なパターンを示さないこともありますのでご注意ください。
腫瘤形成性膵炎TFP
臨床的な概念であり、限局性の腫大や腫瘤像を伴う慢性膵炎です。
アルコールに起因するものと自己免疫が原因となるものがあります。
膵癌との鑑別は難しいと言われております。
MRCPで主膵管を観察しduct penetrating signが陽性であれば腫瘤形成性膵炎で陰性であれば膵癌の可能性があります。しかし鑑別が極めて困難な症例もあります。
duct penetrating sign:主膵管が腫瘤内を貫通あるいは腫瘤内に入り込む像のことで、膵癌では主膵管は拡張し急に途絶します。
膵島細胞腫瘍
T1WIで低信号、小血管を造成し豊富な血液量と水分量を反映しT2WIで高信号のことが多いですが、線維成分に富むとT2WIでも低信号となります。
ダイナミックでは実質と比較し、早期から濃染します。
まとめ
膵臓についてでした。出題数は多くありませんので時間が惜しければ勉強を後回しにしてもいい問題かと思います。僕も得意ではありませんので今回説明も少なめでした。
参考書籍・文献
腹部画像診断の勘ドコロ P111
解答に関して、今まで培った知識や書籍・文献を参考に導出したもので、私の認識不足により間違っている可能性もございます。ご理解いただいた上でご参考ください。
MRI認定試験の合格を目指している方のお手伝いができればと思っています。



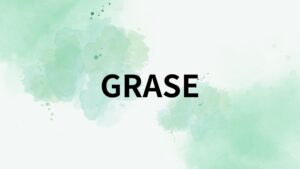

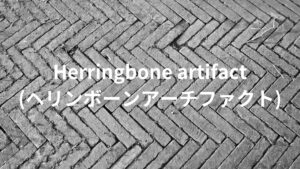



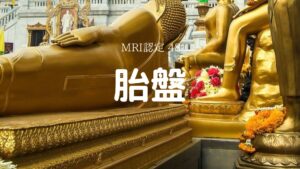

コメント